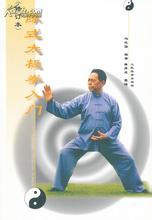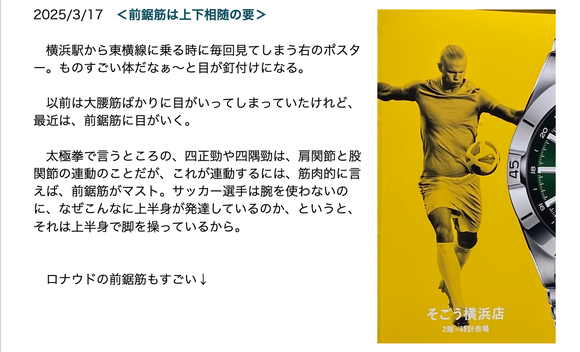

腕と脚の連動というのは、大腰筋だけでなく前鋸筋も大きなポイントになってくる。
前鋸筋が作用することで、肩が体の脇経由で股関節と連動するからだ。それはまさに、経絡の胆経の道筋。
バレエではポールドブラという腕の動かし方の練習で前鋸筋を使って腕を動かす感覚を身につける。太極拳と同じく、肩を上げない、下げておく、というのは前鋸筋を使うための大前提。加えて、前肩猫背では肩甲骨と肋骨が張り付いてしまってその隙間にある前鋸筋の動く余地たないので、前肩は治さなければならない・・・
昨日の練習では、肩を下げてもすぐに上がってきてしまう生徒さんを実験台に、前鋸筋が支えるようになる位置に肩や腕を強制的に動かしてセットしたら、それがうまくハマった!
前鋸筋が入ると、自分でハマった感がある。もう肩は上がってこない。
バレエの先生が「腕をカチッとハメてください!」という意味がわかるの前鋸筋が入った時だ。腕がハマらないと、脚は上がらない。腕がハマらないまま運動をすると無駄に下半身が太くなり動きが鈍くなるのだ。(冒頭のハーランド選手が両手を真横に開いてボールを蹴る様はバレエの腕の2番ポジションでジュテをするのとそっくり)
昨日の生徒さんは、その感覚を得て、続けて動功をした時には、下半身との連動の感覚も得られたようだった。
という私も、前鋸筋がいつもバチっとはまっているわけではない。外れるとまた入れ直さなければならない。太極拳の師などは常に入っている。腰の王子も然り。それは大きな差です。四正勁と四隅勁が完璧になった時には体の歪みもほぼなくなるだろう・・・・も少し頑張らなければならない。
2025/3/11 <膝の曲げ方>
下の動画はバレエの下肢の基礎的訓練だが、膝を曲げる時に膝を動かしてはいけない、という注意点は通常の歩行にも通じるもの。太極拳で言えば、円裆や提膝、あるいは、虚歩(抜き足)とつながる。
実は、この膝の扱い方は上肢の肘でも同じこと。肘を曲げる時に肘を曲げようとするとアウトだ。膝を曲げる時は、太ももの裏側を伸ばすのと同様、肘を曲げる時は二の腕を伸ばす必要がある。そうしなければ、股関節と膝関節の連動、あるいは、肩関節と肘関節の連動はおこらない。
2025/3/9
上腕骨の内旋、外旋は腕と胴体を連動させるためには必須の条件。
太極拳では上腕骨の内旋は腕の逆チャンスー、外旋は順チャンスーにあたるが、内旋、外旋を繰り返すことにより、上腕骨と肩甲骨の連動が深まっていく。もちろんその時に丹田を抜かないのが前提で、丹田を作らずにただ内旋外旋をしても、タコのような動きになってしまう・・・
上腕がうまく使えれば、股関節はとても使い勝手が良くなる。股関節に隙間が空くからだ。逆に言えば、上腕の使い方が下手だと、股関節の隙間ができず、前腿が張ったり膝を痛めたりする。
昨日、今日のレッスンでは、日常生活における上腕(=肘)の使い方の例をいくつか挙げた。太極拳で学ぶものは、日常生活に活かしてこそ意味があるからだ。特に、腕や手の使い方は、日常生活で稽古ができる。
どうやってゴミを拾うのか?
この問いに太極拳的にどう答えるのか?
私は師父の日常動作を観察して多くのことを学んだ。
師というのは一緒にいるだけで多くを学べる存在だ。先生とは違うのだ。
劉師父がものを拾う時、ものを持ち上げる時、その動作を見て、私はおや?と思ったものだ。何度も何度も見て、なるほど、と理解した。上腕を回転させているのだ。
今日のレッスンで生徒さんたちに地面にある物を拾う動作をやってもらったが、何も考えずに拾うのと、師父のように腕を使って拾うという二つの動作を比べたら、いつもの動作がいかに腰に悪いか、体に余計な負担をかけているかが理解できたようだった。
そう、太極拳で学ぶ動きはとても合理的!
私も家事をしていて、時々、この動作は間違えている・・・と気づくことがある。







 太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜
〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~
太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜
〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~